
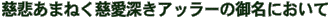
肉体の死滅後の魂
アヴェロエス著
田中千里訳
人間の魂は死滅すると語るのは誤りで、
知られる限りでは、魂は不死で永続し、
死滅も限界も考えられない、
とする人々の論説について。
- アヴェロエスは語る。更に、アルガゼルは次のように述べた。魂は生まれて後に、やがて死滅する、というのは誤りであることについて哲学者達は二つの理論を持ち合わせているが、その一つは、もしも魂が死滅するのであれば、その死滅は三つの事情の一つによる以外には無いのであって、肉体の消滅と共に魂が死滅するか、魂に現れる対立のために死滅するか、強力なもの(神)の力によって死滅するか、である、肉体の消滅に際して魂も死滅する、ということは誤りで、実に魂は肉体から離れているからである、魂に対立が存在するということは誤りで、肉体から離れた実体には対立は無いのである、既に述べられたように、強力なる神の力が非存在に結びつけられる、ということは誤りなのである、とアルガゼルは説明した。
- 神学者達には疑いがあって、アルガゼルは次のように言う。我等は魂が肉体から離れているとのことを認めず、又、アヴィセンナも魂は肉体の数に従って数えられるとのことに意義を認めているが、しかし魂はすべての個別的なものにおいてあらゆる様式で数的にそれぞれ単一である、とのことには多くの不都合が生じるのであり、例えばソクラテスがあることを知る場合にプラトンも又それを知り、そしてプラトンがあることを知らない場合にソクラテスもそれを知らない、ということから(別人の別々の異なる魂による認識が同一であり)不都合になる、とアルガゼルは述べるのである。この立場では別の不都合も生ずるのであって、実際アルガゼルはアヴィセンナの論説に対して、魂が肉体の数に従って数えられる場合には、魂は肉体に結びつけられ、肉体の消滅にあたり必然的に魂も死滅することになる、と言うのである。
- しかしながら哲学者達は、二つのもの(塊と肉体)の間に、例えば望むものと望まれるものとの関係や鉄と磁石の関係が存在するように、結合と愛との関係が存在する場合に、一方が消滅すれば他方も消滅するとのことが起こるわけではない、と言うこともあるのである。しかし反対者達は哲学者達に、魂が個別化されてその数だけ多数化されるもの、そして又、質料(肉体)から離されるものは何であるか、と尋ねることになる。さて、個別的なるものの数の多数化は質料から生ずるが、魂の永続と魂の多数を弁護する人は次のように言うのである。魂は微細な質料からなり、それは諸天体から流出される生命熱、すなわち暖であるが、それは火でもなく、火の原理が中に存在するのでもなくて、この地上に存在する肉体とそれらの肉体の中にある魂とを造形する諸霊魂がその微細な質料の中に存在しているものである、と述べるのである。哲学者達の誰一人として、天からの熱が要素の中に存在して、動物や植物を成長させる力をもたらす、ということを否定はしない。哲学者の中のある人々は、これを天体本性諸能力と呼ぶ。ガレヌスは実に造型能力とそれを呼び、ある時は造物主と呼ぶが、又それは
生物を創造した賢明なる能動者が存在することを知らせる、と語っていて、これは解剖によっても明らかになるのである。実際、この能動者がどこに存在し、何であるか、ということは人間にとって余りに高貴すぎて知ることは出来ないのである。従ってプラトンは、魂は肉体の産出者で、造型者であって、魂は肉体から離れている、との理論を受け入れている。もしも肉体が魂の存在するための条件であれば、魂は肉体を産出することも造形することもない。実にこのような肉体の産出者としての魂は生殖する動物においてよりも生殖しない動物において一層明らかである。魂とは要素的な熱に加えられたあるものであるということを我等が知っているように、調整された知的な作用を熱が引き起こすのが熱というものにおける熱の本性によるのではないから、種子の中に存在するところの熱は産出と造形のためには十分ではない、とのことを我等は知っている。そして、動物や植物や鉱物やその他のすべてのものの中に見出される種の中で多くの種を産出する魂が要素の中に存在すること、種の存在の中には働きがあり、限界のある永続性があり、その種を保持する能力があること等について、哲学者達にとっ
て見解の相違は何も存在しない。さて、これらの魂は、天体の諸霊魂とこの地上で感覚的な多数の肉体の中にある多数の魂との間の言わば諸媒体となり、疑いもなくこの地上に存在する多数の魂や肉体に対して支配権を握るのであって、ここから異論が発生するが、あるいは又、多数の魂そのものがそれらから産出された肉体と、それらの間の相似によって結びつけられるか、いずれかである。そして肉体が死滅すればそれらの魂は、この精神的な質料と、感知されないその微細なものとに回帰するであろう。
- これらの魂が存在することを認めない古代の哲学者は一人もいない。しかしながら、これらの魂が、肉体の中に存在するところのものであるか、或いは、それとは異なる別の類のものであるか等については見解に相違がある。実に、形相の授与者によって魂を説明した人達は、これらの形相を離在的知性であると考えた。あるムーア人の哲学者(イスラム教徒は八〜十五世紀にスペインを支配したが、スペインのイスラム教徒の名称であり、特にここではイブン・バーツジャ〔〜1139〕ではないかと思われる)以外にこの見解は昔の哲学者達の誰にも見出されない。離在的なものによる変化は質料を変えることはなく、元来それ白身による変化である、ということは基本的な理由によるのであって、変化を起こすのは変化させられるものの矛盾対立によるのであり、実際このような論議は哲学において最も深遠な問題である。最も重要なことは、質料的知性は単一の知性的なものであって、無限定のものを知性認識し、一般的判断でそれらについて判断するのであり、この判断での本体は質料からなる(肉体と結びついた)魂の本体ではない、とのことが示される。従って、それは質料(肉体)とは全く関係
がない。このような理由でアリストテレスは、始動因を知性、換言すれば、質料から離れた形相である、と考えたアナクサゴラスを賞賛する。〈アリストテレス『形而上学』「あらゆる存在の自然を生みだす―善くなり美しくなることの原因が―物質であるはずはなく―理性〔=知性〕を、自然のうちにも内在すると見て、この世界のすべての秩序の原因であると言ったとき、この人のみが目ざめた人で、―アナクサゴラスはこうした説をとっていた〉従って、知性は何らか他の存在によって影響はされない。さて他方、質料が受動性の原因であるが、この理由から受動能力における態勢は能動能力においてと同様で、(肉体と結びついた)魂において質料(肉体)を有する受動能力は限定された事物を受け入れることになるのである。
- (注、肉体と結びついた諸能力を意味する魂は、質料である個別的肉体の死と共に滅びるが、質料から離れた知性は、精神的で質料に基づく計算を超越した単一性を有して永遠不滅である、とアヴェロエスは考えた。現代的解釈をすれば知性によって人間共通の真理・文化の永続発展を、個人の死を越えるものとして、説いたと言うことができる。)
|
書名
|
著者
|
出版社
|
出版年
|
定価
円
|
(アルカゼの)『《哲学矛盾諭》の矛盾』
ISBN: 4773348275 |
アヴェロエス著
田中千里訳 |
東京・近代文芸社 |
1996 |
本体2427 |
イスラミックセンターパンフレットのページへ戻る
聖クルアーンのページへ戻る
ホームページへ戻る

