
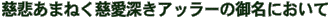
ラスト・バリア
スーフィーの教え
ルシャッド・フィールド著
山川紘矢・山川亜希子訳
鉱物であった私は死に、植物となった。
そして植物となった私は死に、動物となった。
動物となった私は死に、人間となった。
次に死ぬ時、この私は翼と羽根をもった天使となるだろう。
そうであるのなら、どうして、
死による消滅を、恐れなければならないのか?
そのあとは、天使よりももっと高く
舞い上がって、
誰も想像ができないようなものに私はなるだろうに。
メブラーナ・ジャフールディーン・ルーミー
- 丘のかなたから夜明けが訪れ、犬を眠りからさまし、新しい一日の始まりを告げた。ミナレットから祈りの刻を告げる声が聞こえてきた。「アラーフ・アクバール、アラーフ・アクバール(神は偉大なり、神は偉大なり)」祈りを呼びかける声は一日に五回、家々の屋根の上に鳴り響き、そのたびに人々に神と向かい合うように命じるのだった。
- ハミッドがロンドンで教えてくれたとおりに私は体を浄めた。「もし水がなければ、砂で洗いなさい。もし砂もなければ、石で洗いなさい。もし石も手に入らなければ、意思によって自分を浄めて、できる限り過去から自由になって、その瞬間に向きあえるようにしなさい」とハミッドは言った。その朝、私は特に念入りに体を洗い、自分に与えられるものはどんなものでも受け入れるために心を開いておけますように、と祈った。
- 七時きっかりに、私はハミッドの部屋のドアをノックした。彼は部屋の中で私を待っていた。彼は私に自分の真正面の椅子に腰を下ろすように合図すると、何の前置きもなしに話し始めた。「今朝は、君に呼吸について少し教えよう。呼吸とは命の秘密なのだ。なぜなら、呼吸がなければ何事もないからだ。正しい呼吸によって、君が探究したいと思っている道を選ぶことができるようになる。風を考えてみたまえ。風は地表から持ちあげることができるものなら、どんなものでも運ぶことができる。花の香りを運び、木から落ちる枯れ葉を運び、植物の種子を、新しく根を下ろす場所へと運んでゆく。この中に偉大なメッセージが隠されている。我々はこの世界へ息に乗ってやってきて、息に乗って退出してゆく。普通の人は自分の人生を機械的に生きており、死の瞬間まで呼吸のことはまったく忘れている。死に直面した時、人はこの世界で生命だと思っていたものの残りかすにしがみつく。何とか肺に空気を送りこもうとあえぐ時、やっと呼吸のことを思い出すのだ、
- 今朝、私が君に伝える練習は、どんな時にもこれから一生の間、毎日行うことができる。簡単に見えるが、一瞬一瞬がみな違うように、毎日毎日が違う。また、時には集中することができない時もあるだろう。しかし、少しずつ、私がこれから話す事柄の重要性を、わかるようになるだろう。
- まず、物質的な肉体の概念を放棄して、精妙体を浄化する方法を学ばなければならない。これは、肉体を常に形作り続けている目に見えない源に出会うためだ。自分を浄化する方法がわかると、もっとはっきりとものごとを見ることができるようになる。なぜなら、物をはっきりと見る目と心の声を聞く耳を曇らせている思考とその投影が、消滅し始めるからだ、結局、我々を分離させているものは思考なのだ」
- 彼は私に、できるだけ椅子を彼に近づけるようにと言った。私が近づくと、彼は右の手の平を上側に向け、左の手の平を下に向けて、二人の両手を合わせた。こうして作られた輪を通って、私たちの間を流れてゆくエネルギーのうずを私は感じることができた。その結果、一瞬のうちに私の気持ちは静まった。
- 「まず背すじをまっすぐにしなさい。次に呼吸の上がり下がりを観察しなさい。これができるようになるには多くの練習が必要だ。しかし、それだけの努力をする心構えがある者はほとんどいない。自分の呼吸だけに集中し観察できるようになると、自分がいかに思考に支配され、絶え間なくあちこちへと引きずりまわされているか、わかり始めるだろう。そして、その事実を直視したくはないが、自分たちがくるくる変わってばかりいることが、明らかになるのだ。しかし、君は君の感情でもなく、体でもないと同じように、君は君の思考ではない。君は君の思考ではないのに、呼吸をじっと観察して思考に動かされないようにすることがそんなにむずかしいとしたら、何かが間違っているのではないのだろうか?」
- 彼はこの質問をしながら、私が彼の目を見るまで、私の手に力を加えていった。「よく注意して聞きなさい」と彼は言った。「そしてよくこのことを覚えておきなさい。君が不変の「自分自身」を獲得するまで、君には常に迷子になる危険がある。君が意識して呼吸することをマスターした時、君は本当の自分自身である「内なる」存在に出会えるのだ」
- 「私は今日、君に呼吸の三つの側面を紹介しよう。呼吸の科学は一生の学びであるが、この三つの側面は、真剣に受けとめ、実際に行えば、君の人生を変える助けとなるだろう。この三つとは、呼吸のリズム、呼吸の質、そして呼吸の姿勢だ」
- 「西洋においては最近、インドでプラナヤマと呼ばれている呼吸のリズムについて書かれた本が、多く出版されている。しかし、呼吸法のリズムが違えば、それぞれ違う結果を生むということは、あまり知られていない。車が坂道をスピードをあげて登る時と、坂道をゆるやかに下る時では、エンジンのリズムはまったく違っている。車のスピードは同じでもエンジンのリズムはまったく違うだろう。呼吸の科学も、これと同じことだ。リズムを理解することは極めて重要なのだ」
- 彼は口をつぐんだ。私は返事をすべきかどうかよくわからなかった。私が何も言わないうちに、彼は再び話し始めた。「今日、私が君に教えるリズムは「母の呼吸」と呼ばれるものだ。どの瞬間にも何かが「生まれている」。多くの人々はこのことに気づいてはいない。また、最も自然な呼吸のリズム、すなわち、我々の存在を支配している宇宙の法則と最も調和しているリズムを見つけだせば、我々は自然に、この地球の平和の実現に貢献するということも、人々は知らない。
- だから、最も基本的な呼吸のリズムを意識して練習するのが、第一のレッスンである。生命の気が上下に流れやすいように、背骨がまっすぐになっているかどうか確かめなさい。次に七つ数えながら息を吸い込み、一つ数える間息を止め、また七つ数えながら息を吐き出しなさい。そして次の呼吸を始める前に、また一つ数える間だけ休みなさい。つまり、七−一−七−一−七という非常に単純なリズムなのだ。真剣に練習すれば、すぐにこのリズムは身につくだろう。ではこのリズムを私と一緒にやってみよう」
- リラックスしてから、このリズムに身をまかせ始めると、私は非常に軽く感じ始めた。ハミッドはまだ私の手をとっていた。息をするたびに、彼のお腹が上がったり下がったりするのが見えた。このリズムは普段の呼吸とは違っていたので、最初はやりにくかったが、私の内部で何かがゆっくりと目を覚まし始めた。それは、リズムそれ自体とは別のもので、起こっているすべてを見守っている観察者だった。
- 「上出来だ」とハミッドが言った。「ではもっと信頼し、リラックスして目を閉じなさい。そして呼吸するにまかせなさい。あらゆる考えを手放しなさい−−すべての生命の中を流れ、息づいているリズムに身をゆだねなさい。このリズムは七つの法則と呼ばれている。この法則に従うことによって、生命原理の一部としての君自身を確立するのだ。その生命原理は自らの中から完全なものを生むことだけを望んでいる。
- では次の段階に進もう。これは君の呼吸する空気の質に関するものだ。七−一−七のリズムをそのまま続けていなさい。
- 風は、軽いものであれば何でもその翼に乗せて運ぶことができるように、もし、我々がリズムを理解し、正しく集中することができれば、多くのものを呼吸に乗せて運ぶことができる。たとえば、スペクトラムの中から一つの色を選んでその色を自分の体の中に吸い込み、一つひとつの細胞に注ぎ込むこともできる。このやり方は、ある種のピーリングに使われている。また、ピアノの低音のような強力なバイブレーションを吸い込むこともできれば、音の範囲を越えた想像できる限りの細かいバイブレーションを吸い込むこともできる。君はどんなものでも選ぶことができるのだ。火、土、空気、水という元素を吸い込むこともできる。花の香りを吸い込むのと同じやり方で、特定の花やハーブの精を吸い込んで、両者の違いを知ることもできる。呼吸の科学は広大な領域を占めており、これまではごくわずかな者にしか知られていなかった。しかし、今は世界中の人々が理解し始めている。正しいリズムを学び、私が教える知恵を習得すれば、すばらしいことが起こってくるだろう。
- しかし、こうしたことは道を進む上での一つのヒントにすぎない。基本リズムを十分に練習できたら、次はもっと詳しい話をすることにしよう。
- 今日、私が触れたいと思っている第二の側面は、呼吸の配置ということである。風が種子を一つの場所から他の場所へと運んでゆくように、呼吸は体の一部分から他の部分へと、特別の目的をもった意思を運んでゆくことができる。呼吸を正しく配置することによって、体にバランスをもたらす方法を学べるのだ。そうすることによって、変成の術、すなわち錬金術を学び始める。我々はこの地上において、奉仕の人生に献身する意識的人間となって、本来の責任を遂行し始めることができるのだ。
- では私と一緒に呼吸して、さきほど教えたリズムを感じなさい。そして想像できる最も上質の空気を吸い込みなさい。この空気に浄化され、すべての痛みを洗い流そう。一緒に呼吸して、エネルギーが頭の上から下の方へ広がりながら、体を伝って降りてゆくのを感じなさい」ハミッドが言うとおりに、まず体中をリラックスさせて、自分の体が自然に呼吸するのにまかせていると、私は安らぎと、それまでに体験したことのない自由な感覚を感じた。同時に、集中力と意識を失わないように努力しなければならなかった。ハミッドが私の手をさらに強く握った。
- 「では何回か深い呼吸をしなさい。息を吸いこむたびに、意識して、自分自身をバランスの取れた状態にもってゆき、それと同時に、自分の体に責任を持ちなさい。君はこれまで、自分だと思っていた多くのものを手放し、自分の中にある真実を発見しつつある。これは、我々が観察者と呼んでいるものだ。君はこの観察者を毎日少しずつ成長させてゆかなければならない。ここまではるばるやって来たのは、自分に与えられた乗り物に責任を持つことを学ぶためなのだ。この世の中では誇り高く雄々しくあれ。しかし、次の世界では頭を低くたれなさい」
- 私はゆっくりと深い呼吸を続けた。するとすぐにハミッドは目をあけるようにと言った。目を開けると、部屋の様子がまったく違って見えた。まるでこの部屋を初めて見たかのようだった。そこは完壁に平和で、やすらぎに満たされていた。すべてがあるべき秩序におさまっていた。部屋の中にあるそれぞれのものの間に完全な流れがあり、しかもその流れはそれぞれの物の内部にもあった。そこには一体感と互いに認め合う気持ちがあった。椅子もテーブルもヘッドも、すべてがお互いを知っていた。それらはもはや生命のない物質ではなく、生きとし生けるものの一部だった。あらゆるものが意識を持ち、無言の言葉を語っていた。あらゆるものはその真髄において完壁だった。
- ハミッドは私の手を放すと、静かに立ち上がった。そして私のうしろ側にまわって、手を私の頭の上に置いた。それから、その手を私の体の両側に沿って、衣服から五センチほど離して、ゆっくりと下におろしていった。今度は私の横に立つと、私の体の前後にそって、同じ動きをくり返した。そして最後にもう一度私のうしろに立つと、今度は私の肩に両手を置いて、じっとしているようにと言った。強力な熱の波動が彼の手から伝わり、私の全身はびりびりと震えた。それはほんの二、三秒のことだった。彼は再び腰を下ろすと、「これでよし」と言った。「現実の世界のことについて話し始めれば、君ももっと理解しやすくなるだろう。しかし、まずコーヒーを飲んでから朝食としよう。君はトルココーヒーのいれ方を知っているかい?できない?」彼はちょっと悲しそうに首をふった。「では、いれ方を習わなくてはね。毎朝一緒に瞑想をしたあと、コーヒーを作るのを君の仕事としよう。コーヒーと朝食がすんだらまた話そう。今から君は浜辺に散歩に行くとよい。帰った時には私が君にコーヒーを用意しておこう」
- そう言うと、彼は部屋を出て行った。私の体はなぜか力が抜けてしまって、椅子から立ち上がるのが難儀なほどだった。二、三分休んでから、朝の漁から戻ってくる漁船を見に、海へと続く道を歩いて行った。
- 浜辺を歩きながら、私はハミッドの変わり様について思いをめぐらせた。今朝の彼は、ロンドンで私たちが一緒に過ごした時の様子とはまったく違っていた。彼の中に厳しさと、威厳と、どんな妥協をも許さない厳格さが感じられた。以前は日常的な話をしたり、笑ったり、夕食の席で議論するなどの時間が必ずあった。しかし今は、切迫感のようなものが漂っているように思えた。また、私たちがこれまでやってきたことを越えて、私がさらに自分を広げるよう期待されているのを感じた。確かに、私は未知なるものに向かって旅を始めていた。しかし、今になってやっと、もはや後もどりはできないことに気がついたのだった。この男の手に自分をゆだねたのだ。芝居は始まり幕が上がったのだ。しかし、私はその筋書きさえ知らなかった。
- 浜辺から戻った時、ハミッドは中庭に二人分の朝食を準備して待っていた。私たちは無言で食事をし、後片づけをしたあと、ハミッドは私に先に家の中に入るように合図をした。それぞれの椅子に腰を下ろすと、彼は中休みがなかったかのようにすぐに話し始めた。
- 「君がここにいる間、我々は毎朝、勉強の時間を設けよう。これは君にとって新しい体験になるだろう。西洋人は勉強というのは、情報を集めたり、知識を得ることだと思っているようだ。しかし、知識は得ることはできない。このことをよく覚えておきなさい。知識は自らが得るものではなく、与えられるものなのだ。それは君に与えられるべき時に与えられるが、実はそれはすべてすでに君の中にあるものなのだ。教育、つまりエジュケーションという言葉は、ラテン語のエジュケアという言葉に由来している。エジュケアとは、生じる、あるいは産む、という意味なのだ。つまり、外側の情報源から、外部の情報を頭につめこむという意味ではないのだ。私が言う勉強とは、君の中にあって生まれるのを待っているものを解放してやるために、愛と意識の基本的な真理を学ぶということなのだ。君が熱心に学べば、理解は自ずと深まってゆくだろう。しかし、この道で学ぶためには、君はまず、準備を整えなければならない。それでまず練習をするのだ。君は三つの世界、すなわち思考の世界、感覚の世界、肉体の世界のバランスをとることを学ばなければならない。勉強とは頭の中であれこれと考え
ることではない。もし、頭だけで勉強したら、概念だけにとらえられてしまう。もし感覚の世界だけで学んだら、あらゆることを感じるが、方向性を失い、ふわふわした状態になってうろつくことになろう。もし体を鍛えるために肉体的訓練ばかりしていたら、地上的な感覚しかなくなって、高い精神を保つことができないだろう。大切なのはそのバランスなのだ」
- 私は彼の話をさえぎって質問した。「知識は与えられるものであって、得るものではないというのはどういうことですか?」
- 「気をつけなさい。その質問は頭の質問だ。本当の質問ではない。もし、私の話をきちんと聞いていれば、こんな質問をすることなどあり得ないはずだ。君はまだ自分が何か行うことができると思っている。君はまだ本当には学んでいないのだ。私の話をよく聞くがよい。私の言ったことを心の中にしみこませる、こうるさい頭で説明しようとするな、と言ったはずだ。よく聞くことによって学ぶのだ。もし聞きたくなかったらここを出てゆきたまえ。そして用意ができたら、また戻って来るがよい。私には仕事が沢山ある。時間を無駄にしたくないからだ。無駄こそ唯一の罪であり、そこからよくないものすべてが起こってくるのだ。罪とは知識の欠除なのだ。だから、もしわかりたいと思ったら、よく聞かねばならない」
- ハミッドの断固とした反応に私はびっくりした。しかし、最初に心に浮かんだ質問をしたのは、彼の話をしばらく止めて、自分の理性的な頭に彼の話に追いつくチャンスを与えるためだった、ということにすぐに気がついた。その質問を本気で考えたわけではなかった。
- 「すみませんでした」と私は言った。「邪魔する気はありませんでした。ただ理解したかったのです。どうぞ続けて下さい。しっかり聞きます」
- 「きつい話し方をしてすまない」と彼は言った。「君はまだシデに来て二日目だし、まだ旅の疲れが残っている。しかし、ここはロンドンとは違うということを覚えていて欲しい。ロンドンではお互いに学び合い、お互いをよく観察し合って、次の段階を一緒にやるかどうか、二人とも見極めていたのだ。そして、君はここに来てはどうかと言われ、それを受け入れた。今、君は私の家に来た。そして、一瞬一瞬が大切なのだ。私は君のここでの滞在を、できる限り短くしたいと思っている。だから無駄にする時間はないのだ。私は自分に与えられた知識を君に伝えたいのだ。君が他の人々に教えられるように」こう言って彼はしばらく口をつぐんだ。「神への献身とは、神をあらゆる面から学ぶことであり、神を理解するということは、神について、できる限り知ることであり、神に奉仕するということは、神について自分が知っていることを他の人々に教えることなのだ。今は君は信頼し、学び、勉強するのだ。勉強し、さらに勉強するだけだ」
- 「何か読んだほうがいい本はありますか?」と私はたずねた。
- 「もちろんない」と彼は答えた。「何年もずっと本を読んできて、君はどこにたどりついたというのだ?君の頭は理屈や概念で一杯だ。そして道を学んだ者が味わう体験に君はあこがれている。君の真の本質を理解するためには、まず、君の頭につまっている理屈や概念をすべて捨てねばならないのだ。本などはいらない。唯一の本は自然の描くものであり、人生そのものが学びなのだ。情熱的に生きたまえ。この道は重大でまじめなものだから、楽しんだり、喜んだりしてはならぬと誰が言ったのかね?この道こそ、あらゆることの中で、最もおもしろい冒険なのだ。そして楽しむべきものだ。神は完全であり、比較を越えたものであることを知る中から、喜びがはじけ出してくる。いつか、私は、なぜ君は菜食主義者なのか聞いたことがあったね。その時私は、神は完全であることを知っているから、私は肉も食べるのだ、と言ったはずだ」彼はにっこりと笑った。彼の目の中にはいたずらっぽい光があって、私も思わず笑ってしまった。
- 「君がどんな類いの考えや疑問を持っているか、私にはわかっていた。しかし、私は君に私流の考えに変わりなさいと一言ったことはない。私たちは君が正しい食事だと思う食べものを、いつも一緒に食べたものだ。しかし、君もわからなければならない時が来たようだ。あらゆるものを生み出している唯一絶対の存在があり、我々はその唯一の存在から、何ものも切り離せないのだ。この宇宙のすべてのものは完全であり、あるべき秩序を保っている。我々が生きてゆけるように、動物が人間の食べものとして与えられているのは、人生の芝居の一部なのだ。それは救いのプロセスでもある。その救いは人間を通してのみ行われるのだ。このプロセスは錬金術のようなものであり、我々は単に精妙なエネルギーの変換器にすぎない。偉大な教師であるメブラーナ・ジャラールッディーン・ルーミーは次のように言っている。『鉱物であった私は死に、植物となった。そして植物となった私は死に、動物となった。動物となった私は死に、人間となった。次に死ぬ時、この私は翼と羽根をもった天使となるだろう。そうであるのなら、どうして、死による消滅を、恐れなければならないのか?』ここでいう「
私」とは誰なのだろうか?これは偉大なる私、第一の私ではなかろうか?今日はこうしたことをずっと考えなさい」
- 「君の中にはこれまでにあったすべてのもの、これからあるすべてのもの、あらゆる過去の時間、あらゆる異なった王国が存在している。動物の王国は何か違うものだと思うかね?動物を見なさい。動物は草を食べる。そして草はすでにその中に、地中のミネラルと太陽の光、そして、宇宙のその他のエネルギーを取り込んでいる。だから草を食べることによって、動物は鉱物王国と植物王国を自らの中に吸収しているのだ。あるのは、唯一絶対の存在だけなのだ。このことは、我々は自分の呼吸法に対して、責任を持たなければならないということを意味する。これをしっかりと覚えておきなさい。そして、食べようと食べまいと、息を吸い込むたびに、君は動物王国の中に含まれている元素を吸い込んでいるのだと知りなさい。今、息を吸い込めば、君は私がすでに吐き出した空気の一部を吸い込んでいる。君が菜食主義だった時も、君は私が食べ、私によって形を変えられた肉の要素を吸い込んでいたことになる。そのことに気がついていたかい?
- 今朝私が言ったように、人生の秘密は呼吸にある。呼吸を正しく使いさえすれば、すべてを変えることができる。そして、意識的に、すべてを変えてゆく者となることは、生まれてきた我々の義務であり、責任なのだ。
- このことが、どのようにうまくゆくのか、一つの物語を話そう。
- ある時、インドの各地を旅した若い女性が私のところにやってきた。一年間、彼女はオレンジしか食べなかった。これは本当のことだ。オレンジ以外何も食べなかったのだ。この女性は非常に丈夫だった。背に重いリュックをかつぐことができた。理論的には、彼女は完全に衰弱し切っていたはずなのに、実際はこれ以上ないほど健康だった。中近東の何人かの人々に紹介してもらえるかもしれないと聞きつけて、彼女は私に会いにやってきた。私は彼女の食習慣をまったく知らずに、彼女を昼食に招待した。彼女は非常に礼儀正しかったが、出された食べものを見て、恐怖におちいった。十四人の人々がテーブルを囲んでいた。私はオーブンで、キュラソーとグランマニエールを塗ったあひるの丸焼きを作ったのだ。別の男が、上等のボルドーワインを持ってきた。そして食事のしめくくりはシャンパンとレモンスフレだった。彼女はすみません、と言って、自分が特殊な食事をしていることを説明すると、バッグの中からオレンジを取り出して、それをゆっくりと食べた。まことにあっぱれな態度ではあったが、我々の食習慣に怖れをなした彼女は、みんなが話していることが何一つ聞こえなかった。話
の中で、私はそのグループの人々に二人の人物の名前と住所を教えた。彼女がそれが知りたくてここに来たことを知っていたからだ。だが、彼女は聞いていなかった。なぜならば、彼女は、スピリチュアルな師はいかにあるべきか、師は何を食べるべきか等々、概念に捕らわれていたからだ。その女性は非常にがっかりし、それ以上に、我々に腹を立てて去った。
- この話の秘密はこうだ。彼女にはインドに長年教えを受けていた師がいた。その師は禁欲主義者で、彼女に例の食事の仕方を教えた。しかし、その食事法よりももっと大切だったのは、彼の元で学んだ呼吸法だった。呼吸を正しく便うことによって、彼女は必要とするすべてのものを取り入れることができたのだ。本人は知らなかったのだが、彼女は必要なものをすべて異なる王国から取り入れていた。つまり、『鉱物としての私は死に、植物となった、云々』ということさ。わかるかね?
- 彼は黙って、待った。私はまた質問をしようと口を開きかけたが、彼が次に言ったことにびっくりした。
- 「今、君がしようとしている質問は、心から発しているのがわかる。だから、その質問には真剣に答えよう」
- 「私が聞きたいのは、もしオレンジと正しい呼吸だけで必要なすべてのものを取り入れることができるとしたら、あなたはなぜ肉を食べるのですか?」
- この質問は彼にとっては、大笑いするほどにおかしいものらしかった。彼はソファの上にひっくり返り、体中をふるわせて笑った。そして、涙が頬を流れ落ちるまで笑い続けた。「なんてこった。君たち西洋人は」と彼は言った。「なぜわからないのかね?私が肉を食べるのは、肉が好きだからだよ」
- 授業は終わった。彼は一言も言わずに、別のもっと小さな部屋へと消えた。その部屋は、私たちがいた部屋とは、戸口にたらした絨氈によって仕切ってあった。私はしばらくそのまま待っていたが、やがて、中庭を通って自分の部屋へ戻った。午後は浜辺ですごすことにした。日没にハミッドと円形劇場で会う約東になっていたので、休憩し、今朝教えられたことを消化するための時間は、十分にあった。
- 三日前にここに着いてから、余りに多くのことが起きたために、私は夕食で一緒になった例の美しい女性のことをほとんど忘れかけていた。その彼女が部屋から出てきた。前の晩と同じように、両手を体の前に出し、例の青い毛糸が今もまたその手にからみついていた。彼女の世界に急に侵入した自分に当惑すると共に、ものすごく悲しくなった。彼女は私を直接見ることはせずに、頭を少しかしげ、両手の指で私の胸を指差しながら、こちらに向かって歩いてきた。それはあまりにも一心な様子だったので、私は急に怖しくなって、思わずあとずさりしてしまった。彼女が私に取りつこうとしているのではないかと思ったが、それでも、私の方に向けられた手から目をそらすことができなかった。両方の手は祈りの形に組み合わされ、青い毛糸が彼女の手首にからまっていた。
- 私から一メートルほどのところまで来ると、彼女は顔を上げて私の目を見た。彼女の目から、目を離さないようにしながら、私は手をのばして、そっと毛糸を彼女の手から取り除いた。からまった毛糸を全部ほどいた時、彼女は自分の手を初めて見たかのように見ながら、にっこりと笑った。毛糸のかたまりが地面に落ちた。私はそれを拾いあげようとしてかがみこんだ。そのとたん、彼女は悲鳴をあげ、いかにもつらそうにしながら、大声をあげ続けた。そして、そこにひざまずくと、自分の手でその毛糸をまたしっかりとつかんだ。
- 彼女を助けおこそうと手をのばした時、ハミッドが中庭を横切ってかけつけた。彼は私を押しのけると、かがみこんで、手を彼女の手の上にのせた。悲鳴はすぐにやんだ。彼を見上げる彼女は、幼い子供のようだった。ハミッドは彼女の手をとって立ち上がらせると、私に毛糸を拾い集めるように目くばせした。私が立ち上がって毛糸を彼女に渡そうとすると、ハミッドがそれを取った。彼はうつ向いて毛糸にキスをしてから、彼女に手渡した。そして、彼女の肩を抱いて、家の方へ連れて行った。
- 私はのろのろと二人のあとをついて中庭を横切ると、自分の部屋に戻った。あの若い女性は誰なのだろう?彼女がしゃべるのを聞いたことはなかった。おそらく、しゃべれないのだろう。ハミッドが彼女に対する時に見せる同情や、彼女を家へ連れてゆく時の普通でないほどのやさしさから、私は彼女はハミッドの娘なのだろうと思った。しかし、今はまだそのことを聞く時ではなかった。それに、自分に直接関係のないことは質問しない方がよい、ということもわかりかけていた。
- シデに来てから、余りにも沢山のことがあったので、教えられたことのほんの一部分でさえ、自分がわかっていないことは確かだった。今朝、ハミッドが話した話題について、イギリスで二人で議論した時に彼が何か言ったかどうか、思い出そうとした。ロンドンでのディナー・パーティーの時に、ハミッドが言っていた言葉が私の心にひらめいた。「人間は精妙なエネルギーの変換器です。この地上での我々の仕事である「業」とは、この惑星を維持するために、次元を持たない真意をこの次元に移し変えることなのです」
- 心の中にひらめいた彼の言った言葉が、どんなテーマの中で話されていたのか思い出すことはできなかったが、その晩、私は「次元を持たない真意」とは何なのか、誰が、または、何がその「業」を作り出したのかと考えながら、彼のアパートをあとにしたのだった。
- 日暮れ近く、私は日没を見るために、ハミッドと会うことになっている場所へと、浜辺を歩いていった。浜辺には網を繕っている三人の漁師がいたが、他には私しかいなかった。昼食前からずっと、ハミッドの姿は見かけていなかった。私の下の部屋からは、物音一つ聞こえなかった。あの女性はまだハミッドと一緒にいるようだった。
- 私はずっと岩のそばで待っていたが、誰も来なかった。どうなっているのか探るために家に戻る決心をしたのは、もうすっかり暗くなってからだった。家の窓には明かりがともっており、台所からは皿が触れ合う音が聞こえた。私はノックをして中に入った。ハミッドはなぜ来なかったのか、何も説明しなかった。私も聞かなかった。彼は私にそこにすわるように合図すると、黒オリーブと白いチーズとワインを一杯、私の前に置いた。「食べなさい」と彼が言った。「ディナーまでにはまだ少し時間がかかる」私は彼がコンロのそばで野菜を切る様子を見守った。そして、その一つひとつの動きの集中力に気がついた。それはロンドンでも同じだった。食事の仕度をしている間、彼は決して口をきがなかった。料理は非常に神聖な行為であるから、すべてを十分に意識し、尊敬の念を持って行う必要があるからだと、彼は言っていた。「命を与えてくれるすべてのものに対して感謝しなさい」と彼はよく言った。「そして、君自身を神のよき食物にしなさい」
- 私はオリーブをいくつか食べた。それは今までに食べたことがないほどおいしかった。彼がどこで手に入れたのか知りたかった。ハミッドが食事の仕度を終えた時、私はそのことをたずねた。「ああ」と彼は言った。「このようなオリーブを作るには、特別のやり方が必要なのだ」彼は腰をおろし、私は彼にワインを注いだ。「オリーブに乾杯しよう」と彼が言った。「これほどおいしくなるまでには、オリーブは沢山の行程を通ってきたのだからね」そう言うと彼は笑い始めた。テーブルがゆれ動くほどの大笑いだった。「君はロンドンにいた時、これと同じオリーブを何回も食べているんだよ」と彼は言った。「その時、なぜ君は気がつかなかったのかね?。でも、もしその時気がついていれば、それを知るために、はるばるアナトリアまで来る必要はなかっただろう。
- このオリーブを作るには、まず、最高級のオリーブを見つけて買ってこなくてはならない。それを何回かていねいに水ですすいで、塩分を全部洗い流す。わかるかね?」
- いつか同じように作るために心に刻みつけながら、私はうなずいた。「次によく洗ったびんを用意する。完全にきれいなものでなければいけない。その中に洗ったオリーブを入れ、オリーブの上から沸騰したお湯を入れる。オリーブがふくらむ。オリーブが十分にふくらむまで湯をそのままにしておく。ただし、長すぎてはいけない。皮がやぶれてしまうからだ。それから水を捨て、レモンの輪切りをいくつかと、生のミントの葉を加える。最後にびんを一番しぼりのオリーブ油、それもできる限り純粋なもので満たす。これはオリーブのエッセンスだ。きつくしっかりとびんのふたを閉め、四十日間、置いておく。こうして完壁なオリーブができあがる。ついでに言えば、七日目には、もうすばらしくおいしくなっている」
- 私がけんめいに作り方を覚えようとしているのを見て、彼はまた大きな声で笑った。「さあ、テーブルの仕度をして、食べよう。オリーブのことはこれぐらいにして」と彼は言った。
- その晩、私たちは夜遅くまで話しこんだ。ハミッドはその日のできごとについては、何も議論しようとはしなかった。私が何を質問しても、「それはまた別のことだしとか、「そのことを議論する時期はまだきていない」などと答えるだけだった。彼はトルコやペルシャのダルウィーシュのすばらしい物語を話してくれた。「君はこのうちの何人かに会うかもしれない」と彼は言った。「しかし、君が彼らを探しにゆく必要はない。もし、君の意志がはっきりしていれば、誰かが、向こうから君のところにやって来るだろう。しかし、しっかり目を開いていなさい。さもないと、その瞬間を見過ごしてしまうから」
- その晩、彼の部屋を去る前に、お祈りをしなければいけないと、彼が言った。私は彼に、自分には祈りが理解できない、つまり、祈りの意味も目的もわからない、と説明しようとした。「だったら、わかりますように、と祈りなさい」と彼はいらいらして言った。「我々の道では献身が必要なのだ。君の問題は、神を信じていないことだ。自分で信じていると思っているだけだ。もし君が、私が知っていることを知っていれば、君は祈るだろう。しかし、私が今言っている祈りは、形を越えたものだ。それに君の愛や感謝はどこにあるのだ〜一日に何回、忘れずにありがとうと言っているかね?君は百パーセント神のお蔭で生きているのだよ。そしてすべての感謝は神に対してしなければならない。本当の意味で感謝できるようになるまでは、君は常に神とは切り離されている。君が祈りを忘れているのは、自分が神によって生かされていることを忘れているからだ。そのために、祈りが単なる言葉の空虚なくり返しになってしまうのだ。それは祈りではない。私が言う祈りとは、心の祈りであり、生活のすべてが祈りとなる状態のことなのだ。朝は神をたたえて起きる。夜はその日に与えられたすべてに対
して深く感謝して眠りにつく。神は君を覚醒させるために、いばらと共にやってきて、君はその上を歩かなければならないかもしれない。そよ風ややさしい雨としてやって来るかもしれない、どのような形で来ようとも、何をたずさえてこようと、君は常に感謝し、神をほめたたえる必要がある。なぜなら、賛美と感謝は、お祈りの二本の手のようなものだからだ」
- 彼はしばらくの間、沈黙した。「偉大なスーフィーの師が、かつてこう言った。『神を現実とせよ。されば、神は君を真実とす』今晩、今、この意味を理解し始めるのだ。神と直接出会ってみたいとは思わないかね?」
- 拒絶された感じと恥ずかしさを同時に感じながら、私は神に対し、静かに感謝の言葉を捧げ始めた。まるで、言葉が解放されるのを待ちのぞんでいたかのようだった。祈りはそれ自身のリズムを取りはじめた。
- そして、返答があった。感謝の中から喜びが生まれ、それは緊張や疑いを流し去っていった。その反応があまりにも速かったので、私は一瞬、疑いを抱き、目をあけてしまった。ハミッドが私の真ん前にすわっていた。再び目を閉じると、心の中に再び解放される喜びを感じた。
- 私たちはしばらく黙ったまま、すわっていた。自分の部屋に帰るためにやっと立ち上がった時、ハミッドは私に向かってほほえんだ。それは、はるかかなたからのように感じられた。その晩、私たちはそれ以上何も言わずに別れたのだった。
引用:第四章
|
書名
|
著者
|
出版社
|
出版年
|
定価
(円)
|
ラスト・バリア
スーフィーの教え
ISBN 4047912794 |
ルシャッド・フィールド著
山川紘矢・山川亜希子訳 |
東京・角川書店 |
1997 |
1700 |
イスラミックセンターパンフレットのページへ戻る
ホームページへ戻る

